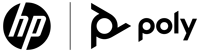昨日午前にはコールセンター/CRMデモ&コンファレンス in 東京の会場にて「センター表彰部門今年度受賞企業から学ぶベストプラクティス」として今年度最優秀ストラテジー部門賞受賞 ネスレ日本様と最優秀テクノロジー部門賞受賞のNTT-ME様両社に最優秀部門賞受賞企業の代表としてダイジェストした内容をご発表頂き、定員を上回る参加者の感心を買いました。
通常のコンタクトセンターとは別に、コミュニティの運営で顧客ロイヤルティを高めた日本ネスレ様の事例はどちらのセンターでも応用して頂きたい内容でしたし、チャットボットの導入展開の教科書的適用事例を紹介して頂いたNTT-ME様の事例も多くのセンターからベストプラクティスとして大いに学びを提供して頂きました。
同様に夕刻のセッションでは、オフィス環境部門の受賞作品紹介並びに表彰式を開催しました。
工夫が凝らされ、整えられた環境でそこに集う人の働く喜びがあふれた作品に対して「オフィス環境賞」として4社が受賞、更に深いこだわりを追求した作品に「オフィス環境賞 優秀賞」を5社が受賞しました。
受賞企業9社の代表者の方々が集い、各社の申請をご覧頂くと共に表彰の喜びに浸って頂きました。
トロフィー授与がメインイベントでしたので作品紹介に多くの時間を割けなかったものの、参加された多くの方々には人が主役のコンタクトセンターにおいて品質や生産性そして永続勤務や働き方などに大きな影響を及ぼす“環境”の先進事例を紹介できたと思います。
既に受賞企業に対しては10月16日時点で受賞の案内をお伝えし、プレスリリースも配信していますが、アワードメンバーの皆様に対しても本日マイページからプレスリリースをご覧頂けるように致しましたので是非アクセスしてみて下さい。
コールセンタージャパン誌では、今年度のセンター表彰部門、個人表彰部門、オフィス環境表彰部門全ての受賞企業の申請内容紹介を記事としてとりあげ一般の皆様にも周知を図ります。
来年度の企画については鋭意検討を重ねており、できるだけ早く皆様に概要をお届けできるよう努力いたしますのでご案内の配信をお待ち下さい。
ということで今年度のイベントはこれにて終了となります。
来年もまた多くのベストプラクティスが集まり、たくさんの議論ができることを期待します。
期間中の皆様のご協力ご支援誠に有難うございました。
オフィス環境部門受賞者決定 – 事務局ブログ【第20回/2025年】
9月17日開催の最終審査会&表彰式では部門賞のトロフィー授与と、当日の発表を審査員が審査して決める最優秀部門賞の表彰が行われたことは前回のブログでも紹介しました。
この日、表彰式では審査員が選ぶ「審査員特別賞」の発表も行われました。
参加企業の相互投票により得票数上位の部門賞候補が選ばれますが、それ以外の申請の中で、この審査内容は専門的、技術的にみて秀逸で業界他社にもぜひ知って頂きたい内容だと評価した申請が審査員特別賞として選ばれています。今年は以下の6社が選ばれました。
● 株式会社NTT東日本サービス
「“使われない補助金”から”使える補助金”への変革
~社会課題から新規ビジネス創出、生成AIによるDX化~」
● 株式会社アイシン
「電話受付負荷低減による職場満足度向上への取組」
● KDDI株式会社
「~頑張らなくて、いい価値を~
デジタルヒューマンによる新たなサポート体験の提供」
● 株式会社アイティ・コミュニケーションズ
「成約ゼロ件コミュニケーターからの脱出!
~AIとコンタクトセンターの二人三脚~」
● エムオーテックス株式会社
「すぐに答えるサポセンなラ、 生成AI使うでしょ!
~AIチャットボット導入から成功までの軌跡~」
参加各社は改めてこれら6社の申請を閲覧して学びを得て頂きたく思います。
<センター表彰・個人表彰プレスリリース>
https://www.cc-award.com/common/pdf/2025_pressrelease.pdf
さて、オフィス環境賞ですが「オフィス環境賞」に4社が選出、「オフィス環境賞 優秀賞」に5社が選定されています。今年度受賞企業は以下の通りです。
【オフィス環境賞 受賞企業】
● 東京ガスカスタマーサポート コンシェルジュセンター 東京・新宿
● きらぼし銀行 相模原カスタマーセンター 神奈川・相模原
● 株式会社NTT マーケティングアクトProCX NTT-WEST i-CAMPUS 大阪・京橋
● アイテック阪急阪神株式会社 i-TEC Prime Center Osaka 大阪・福島
【オフィス環境賞 優秀賞 受賞企業】
● 楽天証券株式会社 カスタマーサービスセンター 神奈川・横浜
● 株式会社朝日ネット CSセンター長崎 長崎・長崎
● 株式会社ジャパネットコミュニケーションズ 札幌オフィス 北海道・札幌
● 株式会社JAL ナビア 天王洲オフィス 東京・天王洲
● 株式会社プレステージ・インターナショナル 岩手BPOフォートレス 岩手・一の関
受賞企業の紹介並びに表彰は11月13日(木)に東京・池袋で開催されるコールセンター/CRMデモ&コンファレンス2025 in 東京にて行います。
人が主役のコンタクトセンターにおいて品質や生産性そして永続勤務や働き方などに大きな影響を及ぼす“環境”の先進事例を知ることができます。定員がありますのでお早めにお申し込みの上是非ご来場ください。
アーカイブ閲覧できるのは今月中です – 事務局ブログ【第19回/2025年】
無事に9月17日(水)の最終審査会&表彰式が終わり、センター表彰部門の審査員特別賞(6申請)、部門賞(9申請)、優秀部門賞(4申請)全てに加え、個人表彰部門のリーダー・オブ・ザ・イヤー賞(9名)、マネジメント・オブ・ザ・イヤー賞(3名)全ての受賞者が決定しました。
受賞者の皆様方おめでとうございます。
そして申請書類の作成、動画作成、プレゼンテーションに多大な労力を注いで頂いた全ての参加者の皆様、お疲れさまでした。
今年度センター表彰部門の参加企業の皆様は、今年度参加32申請全ての1次審査提出資料が閲覧できます。併せて500超にのぼる過去参加作品のアーカイブがご覧頂けます。
お互いに学び合うことを目的に開催しているアワードですので、アーカイブ閲覧は他社の取り組みを知ることができる他に類を見ない参加特典となっています。
会期中はいつでも見ることができるわけですが、これは“会期中”の特典です。
今年度の会期は10月31日(金)が期限となっていますので、ご参加の皆様はあと4週間のうちに過去の英知の集合から沢山の学びを得て頂きますよう、お願いします。
また、審査員が今年度参加申請のすべてに対して印象・感想・評価をコメントしてご覧頂けるようにしています。これは10月8日(水)には参加各者のマイページからご覧頂くことができますので、是非参考になさってください。
今年度の表彰制度では、オフィス環境部門の審査・表彰が残っています。
こちらは11月13日(木)に東京・池袋で開催されるコールセンター/CRMデモ&コンファレンス2025 in 東京にて受賞作品の紹介並びに表彰を行います。
人が主役のコンタクトセンターにおいて品質や生産性そして永続勤務や働き方などに大きな影響を及ぼす“環境”の先進事例を知ることができます。是非ご来場ください。
最優秀部門賞、審査員特別賞受賞おめでとうございます– 事務局ブログ【第18回/2025年】
昨日東京・両国KFCホールで開催された最終審査会にて2025年度センター表彰部門最優秀賞受賞申請が決定しました。
ファイナリスト(9申請)のプレゼンテーションはいずれも素晴らしいものでした。
参加者による投票で選ばれたファイナリストですから、発表時間の20分にはそれぞれ納得のシナリオと独自の工夫、新鮮さがあふれていました。
DX化が進む中、AIを使いこなす手法や適用の実際、人とシステムのうまい融合の仕方、そして人でなければできない顧客対応の追求といった現代の課題と対処策がふんだんに語られました。
年々プレゼンテーションの表現力も向上しており、DX時代にふさわしいリテラシーの高さを感じる発表会でした。
最優秀部門賞に選ばれた4社の申請を紹介します。
オペレーション部門最優秀賞は明治安田生命保険相互会社様の「「感動」をお届けするための明治安田センター革新 ~センターの未来を創造し、お客さまの期待を超える~」です。全社組織を巻き込んだコンタクトのピークアライバル対策やデジタル窓口の強化、そして包容力のあるセンタースタッフの働き方意識改革など全方位の施策展開を進めた軌跡を紹介されました。全社的かつ複合的な施策展開の重要性とその効果が良く分かります。
テクノロジー部門最優秀賞は、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー様の「最新技術と共創するコンタクトセンターへの挑戦 ~生成AIチャットボット導入・活用ストーリー~」です。
あまたある生成AIの中から何を選び、どのような工夫と段階を踏んで成果を生んだかの軌跡が語られました。ツールとしてのAI導入・展開のお手本となる事例です。
ピープル部門最優秀賞は初出場の関西ビジネスインフォメーション株式会社様の「現場ファーストのナレッジマネジメント ~そこに愛はあるんか?ツールだけではないナレッジ共創へのアプローチ~」申請です。
センター運営の1丁目1番地である「ナレッジ」を再整備・再構築する過程と、それを”人“が使うための愛ある展開の工夫が共感を呼びました。
ストラテジー部門最優秀賞はネスレ日本株式会社様の「「“受け身”卒業。コンタクトセンターが仕掛けた逆転劇」です。リモートで顧客対応を行うことはセンターの得意技。通常のコンタクト対応ではない“コミュニティ”運営もセンター主導でやればロイヤルティの高い顧客を作り出すことができ繋がりを紡ぐことができる、というどちらのセンターにも応用してもらいたい事例でした。
いずれも甲乙つけがたい発表をして頂いたファイナリスト各社の申請はそれぞれの申請部門賞を受賞しました。
また、同時に発表された個人表彰部門では、リーダー・オブ・ザ・イヤー部門受賞者9名、マネジメント・オブ・ザ・イヤー部門受賞者3名の受賞発表ならびにトロフィー授与が行われました。
センター表彰部門、個人表彰部門の受賞者は↓に掲載しておりますのでご覧下さい。
センター表彰にご参加頂いた皆様には審査員の印象・コメントを10月8日(水)にはフィードバック致しますので楽しみにお待ちください。
最終審査会は9月17日!– 事務局ブログ【第17回/2025年】
8月22日にはメットライフ生命保険様、朝日ネット様のセンターに訪問するセンター視察in 長崎を敢行し、定員を上回る大勢の参加者を迎えて大変盛り上がりました。
7月に開催したアルティウスリンク様に伺ったセンター視察 in 山形もそうでしたが、実際にセンターに入ると独特の空気感がありますし、社風・文化を感じることができます。在宅がニューノーマルになっているとはいえ”人“が資産のコンタクトセンターですから組織体制の在り方とあるべき環境について考えないわけにはいきません。県民性や勤務態度、DX化の流れの受け止め方など他社のセンターへ行って分かることや、納得できる採用や能力開発の施策、日々のモティベーションの維持の方法等学ぶべきことが沢山ありました。
今年の2回のセンター視察はそれぞれ猛暑の中でしたので移動の際にも参加された皆様にはご負担をお掛けしましたが、その暑さ以上に皆様からの“機会あれば是非他社センターへ訪問したい”思いは感じましたので来年度も引き続き企画したいと思います。
うちのセンターに是非来て欲しいという方がいらっしゃいましたら事務局にご連絡をお願いします。
さて、2週間後の9月17日(水)にはいよいよセンター表彰部門の最優秀賞を決定する最終審査会を開催します。
参加各社の投票で選ばれた9申請の皆様が、オペレーション、ストラテジー、テクノロジー、ピープルそれぞれ4部門の最優秀賞獲得にむけてプレゼンをします。
AGENDAをご覧頂いてもお分かりの通り、ほとんどの発表内容に多かれ少なかれ顧客向けDXのチャットBOTや音声認識、テキストチャットやメール、メッセージの自動生成等が含まれていたり、オペレータ支援のDXとしてAIアシストやトレーニングツール制作のDX化等対応品質強化の施策が報告されていたりします。
そういった施策を説明するにあたって最終審査会では音声出力や編集されたビデオを流すこともできるので各社工夫を凝らして分かりやすいプレゼンを単会されることと思います。
シナリオは変わりませんが、1次審査会とは異なる表現力を見ることができますので今年度参加各社も是非お越し下さい。
最終審査会のプレゼンは1回限り、会場でのリアルプレゼンでしか聞くことができません。オンライン視聴もできません。プレゼン資料もアーカイブ対象になっていませんので聞きたい場合は会場にお越し頂かないといけません。
今年参加されていない一般企業の方も有料のチケットを購入頂ければ聴講可能です。
ご都合つく方は是非ご参加下さい。
マイページからお申し込みをお願いします。
最終審査会では先に審査を終えている個人賞2部門の表彰式も執り行います。
個人賞表彰式後には、立食形式のパーティの中で審査員特別賞の発表と表彰、そしてセンター表彰部門の部門ごと最優秀賞審査結果を発表します。
多くの皆様のご参加お待ち申し上げます。
最終審査会AGENDA公開 – 事務局ブログ【第16回/2025年】
9月17日(水)開催のセンター表彰部門最終審査会のAGENDAを公開しました。
こちらからご覧ください。
今年度参加各社の投票による得票上位を獲得した9申請が選ばれ、改めて最優秀部門賞をかけて発表して頂くことになります。
今年度ファナリストの横顔をご紹介します。
オペレーション部門賞では3申請がノミネートされています。
●AI相手のロープレで研修効果を高めて新人の即戦力化を果たしたNTTフィールドテクノ様。
●カスハラ被害を予防するためにセンター側から節電する対処を実施したアルティウスリンク様。
●顧客期待に応えるためのあらゆる施策を全方位で実施した明治安田生命保険様の3社の発表です。
ストラテジー部門は2申請の対決です。
●戦略的なチャットボット強化策で成果を上げたKDDI様
●コミュニティを活性化させ企業ロイヤルティを高めたネスレ日本様の2社による発表です。
テクノロジー部門は2申請の発表です。
●効果的な生成AIの導入・活用の方法とその成果はNTT-ME様
●同じく生成AIと人との融合で価値創出を図るNTTマーケティングアクトProCX様
ピープル部門はやはり2申請となります。
●運営基盤強化のイロハのイであるナレッジを作り込み運営に活かす関西ビジネスインフォメーション様
●優秀オペレータの挙動をアイトラッキングしてノウハウ展開を図るNTT-ME様の発表です。
いずれも甲乙つけ難い優秀作品であり、自社にも応用できそうな内容となっています。
さて、この最終審査会には今年度アワード不参加の会社でも聴講参加して頂くことができます。
これだけの内容を1日で学ぶことができる機会はありませんので、お時間都合つけて頂いて是非ご参加下さい。
マイページからお申し込み頂けます。
最終審査会では先に審査を終えている個人賞2部門の表彰式も執り行います。
個人賞表彰式後には、立食形式のパーティの中で審査員特別賞の発表と表彰、そしてセンター表彰部門の部門ごと最優秀賞審査結果を発表します。
参加企業の皆様はもちろん、多くの皆様のご参加お待ち申し上げます。
オフィス環境部門申し込み締切り迫る – 事務局ブログ【第15回/2025年】
猛暑で外を歩くのは億劫です。
快適な環境でオフィスワークができるコンタクトセンターは天国ですね。
もちろん通勤の必要のないホームワークも有難い環境です。
とはいえ、全国津々浦々求人には苦労されているセンターも多く、これからも採用難が続くことも当たり前に予想できるのでその対策も急がれます。
お客様に満足を提供するには、それ以前に従業員満足が不可欠だということは自明の理ですが、その従業員満足に大きく影響がある要素の1つが”オフィス環境“です。
どんな通勤アクセスで、どんな空間で、どんな設備で、どんな食堂や休憩のスペースが用意されているかで従業員の働くモチベーションと継続的な働きたい意向は大きく変わります。
今勤務されている高品質な応対ができる方々の在職年数も環境次第で違いが出ます。
当アワードでは2013年からこの環境に着目し、働きやすい環境を提供されている施設にスポットライトを当てる活動を行ってきました。
これが「オフィス環境表彰」です。
3年に1度の開催となり、今年が第5回目の審査となります。
過去4回の審査では累計34施設を表彰してきました。
毎年行っているセンター視察の訪問先として、オフィス環境賞受賞企業の施設に伺っていますがご参加頂いた皆様からは異口同音に「こういう施設で働きたい」と感想を頂いています。
勤務されている方々の退職率も著しく低いことが証明されています。
ちなみに8月22日に予定しているセンター訪問では過去受賞施設のメットライフ生命様長崎本社に伺うことにしています。
今年はどのような施設の応募があるでしょうか。大変楽しみです。
このオフィス環境賞の応募締め切りは来週8月8日(金)です。
うちのセンターも応募してみようという方は、まだ1週間ありますので申請資料はお作り頂けると思います。
今回のがすと次の開催は3年後ですので是非申請はお急ぎください。
1次審査会終わりました – 事務局ブログ【第14回/2025年】
猛暑の中、先週金曜日18日には東京・池袋のサンシャインシティ・コンファレンスルームにてセンター表彰部門の1次審査会が開催されました。
4会場に分かれて今年度参加の30申請全ての発表が行われました。
参加された22社の内、初出場は7社でした。
発表されたセンターの皆様、お疲れさまでした。
発表者の方は自社の発表が終わるまではなかなか他社の発表を聞く余裕はなかったかもしれませんが、1日でこれほど多くのセンターの実情を知る機会はあるものではありません。
多くの学びがあったことと思います。
どのセンターも業種業態、組織の規模を問わずボイス、ノンボイスの運用を問わず様々なテクノロジーを展開されており、多かれ少なかれ生成AIを含む広義のDX化活用事例が発表され、顧客応対業務における生産性向上やオペレータ支援と働きやすさの醸成に大いに貢献している実態を知る事ができました。
AIと共存する環境で人がどのようにAIと向き合わなければならないか、は各社各様の工夫や考え方があるようです。
顧客応対を企業価値向上の戦略的要素としてとらえて施策実行されているところも参考になりました。
これから8月8日を期限として参加各社の投票が行われ、9月17日に開催される最終審査会に駒を進めるファイナリストの選定に入ります。
ファイナリストによる最終審査会には一般参加も可能ですので各社の取り組みをお知りになりたい方は是非お申し込みください。
さて、現在絶賛申し込み受付中の今年度第2弾のセンター視察は8月22日開催、場所は長崎です。
2年ぶりの長崎訪問となりますが、今年は贅沢にもメットライフ生命保険様と朝日ネット様の2つのセンター訪問となります。
AGENDA等詳細は↓をご覧ください。
https://www.cc-award.com/event/event.php?id=120
盛り沢山の学びがあります。
ご都合つく方はこの機会に是非長崎へ。マイページからお申し込みください。
沢山のご参加お待ち申し上げます。
長崎でお会いしましょう – 事務局ブログ【第13回/2025年】
先週11日はセンター視察企画の今年度第1弾、アルティウスリンク様やまがたワークプレイスに訪問しました。大勢のご参加をいただき講演・視察・交流会と学びの多い1日でした。
山形に続き今年度第2弾のセンター視察は長崎です。
8月22日(金)長崎のメットライフ生命保険様本社に集合、視察の後、朝日ネット様のセンターに移動します。
そちらで視察・講演を聞いた後、今度はジャパネット様が昨年10月にオープンした長崎スタジアムシティに移って交流会を行うという贅沢な企画です。
AGENDA等詳細は下記のURLからご覧ください。
https://www.cc-award.com/event/event.php?id=120
保険会社、通信会社、運輸、通販その他多くのセンターが集積する長崎です。2年前にも長崎でオリックス生命様とANAテレマート様2社のセンター視察を開催しましたが、定員を超えるお申し込みがあり全ての方々のお申し込みを受けることができませんでした。
なかなか1回では長崎の素晴らしさを伝えきれませんので今回2回目の開催となります。前回ご参加頂けなかった方は是非この機会にご参加ください。
盛り沢山の学びがあります。
ご都合つく方はこの機会に是非長崎へ。マイページからお申し込みください。
さて、センター視察の翌週18日(金)はセンター表彰部門の1次審査会が東京・池袋で開催されます。
今年度参加の30申請全ての発表が聞ける1日です。
過去参加企業の方は有料となりますが聴講可能です。
過去参加企業一覧にて参加の有無をご確認の上お申し込みください。
沢山のご参加お待ち申し上げます。
個人表彰部門申し込み締切りは6月25日(水) – 事務局ブログ【第12回/2025年】
本日センター表彰部門の1次審査会AGENDAを公開しました。
今年の参加は25社30申請となりました。
従来からのDX化の潮流に加えて、AIの展開、AIエージェントの活用に関する申請が多いようです。
もちろんそれを実現する人に焦点を当てた内容も多くあります。
参加企業の皆様は7月18日(金)の1次審査会に向けてご自身の発表準備と他の参加者のどの発表を見るかご検討をお願いします。
今年参加されていなくても、過去に参加された企業の方はゲストとして参加可能です。(有料です)
マイページからのお申し込みお待ちします。
実際にセンターへ行って運営や文化を学ぶセンター視察企画の今年度第1弾、アルティウスリンク様やまがたワークプレイス訪問は絶賛申し込み受付中です。
AGENDA等詳細は↓をご覧ください。
https://www.cc-award.com/event/event.php?id=117
盛り沢山の学びがあります。ご都合つく方はこの機会に是非山形へ。マイページからお申し込みください。
さて、申し込み締め切りまであと1週間を切ったのは個人表彰部門です。
6月25日(水)が期限です。
センター運営、マネジメントには専門知識とスキルが要求されます。
企業ごとに組織体制は異なりますが、それぞれのポジションや職務管掌でこのセンターにこの人ありというリーダーシップを発揮している方々が必ずいらっしゃいます。
モチベーション強化に年1回しか訪れない個人表彰部門の応募機会です。是非スポットライトを当ててあげて下さい。
自薦他薦を問わず応募できます。
応募書類はこの週末にでも作成頂くこと可能です。
ご応募お待ち申し上げます。